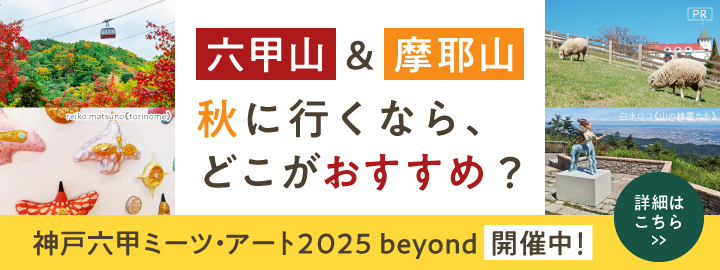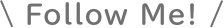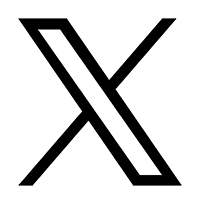写真で見る関西のいま、むかし ~第1回 川西能勢口駅編~
2025.10.13おでかけ
鉄道会社と人々をつなぐ接点といえる「駅」。そのすべてにはさまざまな歴史があり、ある駅は昔のまま、ある駅は大きく姿を変えながら、今日も皆さんの生活を支えています。
このシリーズでは、阪急・阪神沿線を中心に昔の写真を掘り出し、今の姿と見比べながらご紹介します。記念すべき第1回は、阪急宝塚線の川西能勢口駅です。

のせでんの開通に合わせて誕生
川西能勢口駅が開業したのは、大正2(1913)年。阪急宝塚線が開通したのは明治43(1910)年ですから、そこから3年間は駅がなかったということになります。
駅ができたきっかけは、「のせでん」こと能勢電鉄。当時は「能勢電気軌道」という名前だった同社が、ここから一の鳥居駅までの路線を開業するのに合わせ、その乗換駅として建設されました。つまり、川西能勢口駅の歴史は阪急電鉄だけでなく、能勢電鉄とも深く関わっているのです。

ここで、のせでんの歴史について触れておきましょう。
のせでんは当初、主に2つの役割が期待されていました。一つは能勢妙見山への参詣客輸送、そしてもう一つはサイダーをメインとする貨物輸送です。
実は、のせでんの平野駅近くでは炭酸水が湧き出ており、明治40(1907)年からは「三ツ矢サイダー」(当時は「三ツ矢印 平野シャンペンサイダー」と呼ばれていたそうです)が作られていました。ここで作られたサイダーは荷車で国鉄の駅へと運ばれて全国に出荷されていましたが、のせでんはその輸送の一部を担うことになったのです。
サイダー輸送はのせでんの収入に大きく貢献。開業当初の旅客収入が1日平均約85円だったのに対し、サイダーの貨物収入は約82円と、ほぼ同等の規模があったようです。

もっとも、大正2(1913)年の開業当時、のせでんの線路が伸びていたのは川西能勢口駅まで。ここから国鉄の川西池田駅までは、依然として荷車に頼っていました。
そこでのせでんは4年後に、国鉄の駅前まで路線を延伸。のせでんと国鉄は線路幅が違うため貨車の直通はできず、ここで荷物を積み替える必要があったものの、以前と比べて格段に便利となりました。

一方、この区間ではもちろん旅客列車も運行されていましたが、国鉄福知山線は昭和56(1981)年まで電化されておらず、日中の普通列車は1時間あたり1本もないというのんびりした路線でした。
のせでん沿線から国鉄に向かう乗客も少なかったため、1950年代には妙見口方面からの直通列車がなくなり、川西能勢口~川西国鉄前間(当時はそれぞれ「能勢口駅」「池田駅前駅」でした)のわずかな距離を、1両編成の電車が行ったり来たりするだけに。やがて朝夕ラッシュ時のみの運行となり、昭和56(1981)年に廃止されました。

その後、この区間の線路は撤去されて市道となりましたが、川西能勢口駅北側の道路脇には線路があったことを示すモニュメントが設置されています。

また、阪急宝塚線の線路をくぐる前後の急カーブもそのまま。昔の写真と見比べれば、往時の風景を思い浮かべることができるでしょう。




改良工事や高架化で姿が大きく変化
さて、川西能勢口駅は前述のとおり、もともと「能勢口駅」という名前でした。現在の駅名になったのは、昭和40(1965)年のこと。4月にのせでんの駅がいったん「川西駅」となり、3か月後の7月に阪急・のせでんとも現在の「川西能勢口駅」へと改称されました。
なぜ、のせでんの駅がいったん川西駅となったのかは、のせでんにも資料が残っていないため分からないとのこと。どんな理由だったのか気になるところです。

川西能勢口駅はこの頃から、徐々に姿を変えてゆきます。当時、阪急の駅は複線の本線を2本のホームが挟む形、のせでんの駅は単線の本線に面したホーム1本とその北側にホームがない側線という構造で、改札口も別々に設けられていました。

昭和41(1966)年、のせでんの複線化を前に改良工事が行なわれ、のせでんのホームは2本に。昭和55(1980)年には阪急とのせでんの連絡改札口が設けられ、利用者は改札を出ることなく両社線を乗り継ぐことができるようになりました。


これらは、沿線の開発などによって阪急・のせでん双方の利用者数が増加したことによるもの。特にのせでん沿線では住宅地開発が大きく進み、昭和53(1978)年には日生線(にっせいせん)も開業したことで、通勤通学客が激増しました。
阪急宝塚線では昭和57(1982)年に阪急初となる10両編成の列車が登場しましたが、川西能勢口駅は駅のすぐ近くに踏切があってホームが延伸できないため、踏切を塞ぐ形で停車。列車の本数が増えたことで踏切が閉まっている時間も長くなり、不便が生じるようになりました。

そこで阪急は川西能勢口駅の高架化を決め、昭和61(1986)年に工事を開始。まずは下り線が高架化され、平成4(1992)年には上り線の高架化も完了しました。さらに、平成8(1996)年にはのせでんのホームも高架上に。その翌年には現在の3号線が完成し、現在の姿となりました。

この高架化により、川西能勢口駅は従来の場所から西へ180mほど移動した一方、さまざまな改良がなされました。
ホームは10両編成に対応し、すべての車両のドアが開けられるように。ホームの数も増え、列車の待避が可能となりました。
また、のせでんの本線は駅を出てすぐのところに急カーブがあったため、それまではのせでんの車両しかここを通ることができませんでしたが、高架化に合わせてカーブを緩やかにすることで、阪急の車両も直通できるようになりました。

そして、これらの設備を最大限に活用して生まれたのが、直通特急「日生エクスプレス」です。阪急とのせでんは、この川西能勢口駅を見ても分かる通り開業当初から深い関係にありましたが、直通列車が運行されるのは初めて。のせでん沿線から梅田エリアに直通できることから、現在も好評を博しています。
ちなみに現在、「日生エクスプレス」は阪急が所有する8両編成で運行されていますが、ごくまれにのせでんが所有する唯一の8両編成・6000系6002編成が充当されることも。見かけたらラッキーです。
周辺には癒やしスポットやスイーツの名店が!
高架化以降の川西能勢口駅は、南側と北側の双方にロータリーが整備されました。規模が大きい南側には、阪急百貨店や多彩なショップ、川西市立図書館などが入る複合施設「アステ川西」があり、終日にぎやか。JR川西池田駅とつながる歩行者デッキもあり、特に通勤時間帯は多くの人が行き交っています。
ちなみに、阪急百貨店は令和7(2025)年5月に大規模リニューアルを終え、新しい郊外型百貨店「川西阪急スクエア」へと生まれ変わりました。


一方、駅の北側も再開発やリニューアルが進行。令和4(2022)年には歩行者デッキで結ばれている建物が「ラソラ川西」となりました。
また、徒歩10分ほどの距離にある「キセラ川西せせらぎ公園」は、建設にあたって市民を交えたワークショップを開催。川西市の北部にある里山からクヌギを移植したり、腹筋ベンチなどの健康器具を備えたりとさまざまなアイデアが盛り込まれています。
地元の人々と宝塚線沿線の中学・高校が連携し、ホタルの幼虫を公園内のせせらぎに放流する取り組みも行なわれており、“都会の中の癒やしスポット”として人気です。


ところで、川西能勢口駅がある川西市は「いちじく」の名産地であるのをご存知ですか?
川西はもともと果物の栽培が盛んだったのですが、昭和初期に北米原産のイチジクが持ち込まれ、栽培に成功。手掛ける農家が徐々に増えるとともに、改良された品種「枡井ドーフィン」が他県にも広まり、今では国内のいちじくの大半を占めるようになったそうです。

そんないちじくを使ったスイーツを提供しているのが、駅北側にある「ケーキのおおたに」さん。果肉をドライフルーツにしてたっぷりと入れたパウンドケーキやパイ、ジャムが人気のほか、旬の時期には生いちじくを使ったタルトやケーキも販売しています。駅周辺を散策される際に立ち寄ってみてはいかが?



「ケーキのおおたに」の詳細はこちら▼
ケーキのおおたに公式HP
写真提供:阪急電鉄、能勢電鉄
この記事を取材したのは 伊原 薫

鉄道ライター
大阪府生まれ。京都大学交通政策研究ユニット・都市交通政策技術者。大阪在住の鉄道ジャーナリストとして、鉄道雑誌やWebなどで幅広く執筆するほか、テレビ出演や監修、公共交通と街づくりのアドバイザーとしても活躍する。
【X】@yakumo0323
【Instagram】@ihara.kaoru
- 掲載店舗や施設の定休日、営業時間、メニュー内容、イベント情報などは、記事配信日時点での情報です。新型コロナウイルス感染症対策の影響などにより、店舗の定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。また、お出かけの前に各店舗にご確認いただきますようお願いいたします。
- 価格は記事配信日時点での税込価格です。